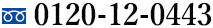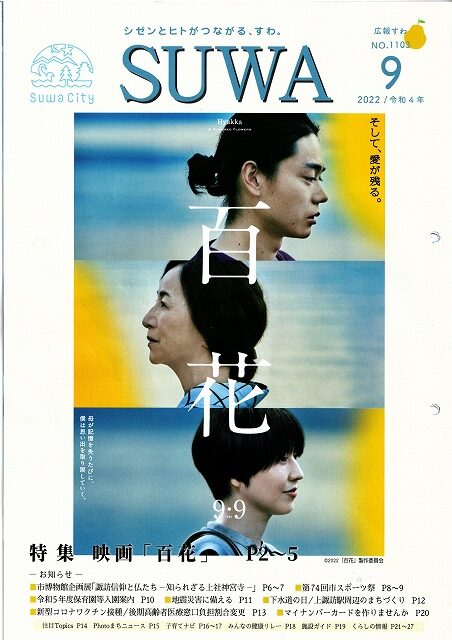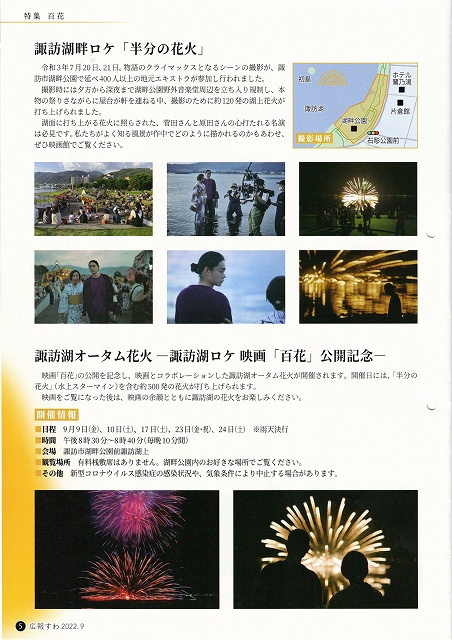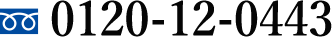「デアゴスティ-ニ」というのをご存知かと思います。
よくCMで見る毎週パ-ツを購入していって、完成品を組み立てるというあいつです。
「週間ウルトラホ-ク1号」でたんですよ❗
昭和のオジサマ方 少年の頃プラモデル作りが何よりの娯楽だったでしょう・・
むろん ”ガンプラ” の前ですよ
私を含めたそんな世代のオジサマ方にはたまらない一品
ふとそんな話を御柱準備作業中に地域のオジサマ方にもらしたところ・・
「あれ 完成させるまでに20万円以上かかるよ」
マジかっ!!
あわてて調べました
ちゃんとその辺の解説をしてくれるサイトがありました。
「週間ウルトラホ-ク1号」全110号
創刊号のみ490円 2号以降は1,990円
とすると合計は・・217,400円💨
そうだったのか・・
ああああ💧
でもなあ なんといっても完成品は全長87.5cm 全幅50cm 全高19.5cm
というビッグスケ-ル そのくらいの値段になるよなあ
さらにさらに
分離・合体はもちろん、発光や音あり
劇中の設定を徹底考証して作り込んだリアルな内部構造
ウルトラセブン55周年の記念イヤ-のビッグアイテム!
他では手に入らないオンリ-ワン
大人の趣味として毎月払える価格(毎月の支払は7,960円 これを約2年間)
おうち時間を充実させる投資として悪くない
この投資により、ファン胸熱のビッグスケ-ルなウルトラホ-ク1号が完成するのです!
そこに価値を見いだせるならば投資する意味あり!
とまあアオッてくれちゃいますが、わかってない・・
”投資” する意味わかってます 胸を熱くさせたい が、しかし
”投資” するお金がないのです😭
ねっ 毎月奥様からいただくお小遣いで、綱渡りの資金繰りをされているお父様方
そうでしょ
もしも ”投資” の話を切り出したら・・
”はっ 何が投資なの? 要するにオモチャをねだる子供と同じじゃん
そもそもウルトラホ-ク1号って何?”
違う! 違うんだ!! これはオモチャではない 男のロマンなんだあっ
そう心の中で叫ぶことにしましょう
今日は風が強い💨
台風がきているせいか・・
こう風が強いと気になるものがあるのです・・

小宮の御柱祭 最盛期のこの時期
あちこちの道沿いには ”流しおんべ” と呼ばれる飾りつけが登場します。
私も地元の飾りつけ作業に参加したのですが、竹ザオを使って設置したこの区間
うねっているなあ・・

いやね 電柱を使って縛り付けている場所はいいのですが、
竹ザオの区間はもしサオが倒れたら・・
通行中の車や人にご迷惑をかけることが起きないかと、心配がつきないのですよ・・

今日のお昼頃で風速は9m
このくらいだったら大丈夫だが、台風なみの強風が吹いたら💨
諏訪地域の御柱関係の役員さまは、同じように心配されていることと推察申し上げます。

今回は金や銀、赤や緑の ”キラキラテ-プ” をふんだんに使ったんですよ💖
あとひと月くらい、がんばってね👍 小松 明